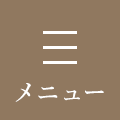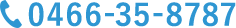- アスリート・運動愛好家の方へ
- 女性アスリートのためのコーチング
- オーバートレーニング症候群
- アスリートのキャリアアップ・コーチング
- アスリート・運動愛好家のためのメンタルコーチング
- コンディショニング
アスリート・運動愛好家の方へ
 競技パフォーマンスの向上や継続的な成長には、フィジカルだけでなく「メンタル」の安定と強化が欠かせません。
競技パフォーマンスの向上や継続的な成長には、フィジカルだけでなく「メンタル」の安定と強化が欠かせません。
当院では、スポーツ現場で起こる心の課題に正面から向き合い、アスリートが本来の力を発揮できるように、また、運動愛好家の方々が、運動を楽しみながらパフォーマンスアップできるように、専門的なメンタルサポートを提供しています。「試合で実力が出せない」「身体が思うように動かない」「引退後の進路に不安がある」などのお悩みに寄り添い、トップアスリートから運動愛好家まですべてのアスリートの方の問題解決の糸口を共に探していきます。
女性アスリートのためのコーチング
女性アスリート特有の悩みに寄り添う
― メンタル×フィジカルの総合的サポート ―
 競技に打ち込む女性たちの中には、月経不順、PMS(生理前症候群)、無月経、貧血、疲労感、気分の落ち込みなど、「女性特有の不調」と向き合いながら競技を続けている方が少なくありません。
競技に打ち込む女性たちの中には、月経不順、PMS(生理前症候群)、無月経、貧血、疲労感、気分の落ち込みなど、「女性特有の不調」と向き合いながら競技を続けている方が少なくありません。
当院では、女性の精神科医、公認心理師に加え、トップアスリートの専属トレーナーが連携し、こうした女性アスリートの身体と心、両面からのトータルサポートを行います。
また、東洋医学や栄養、運動科学も取り入れながら、「ネオヒーラー」を用いた施術を行っています。東洋医学の観点から脈診・腹診等を通して、自律神経やメンタルの揺らぎまで含めて全体を把握、あなた自身の「回復力」を引き出すことを大切にしています。
見えない不調に振り回されることなく、自分のリズムでパフォーマンスを高めたい、そんなあなたのためのコンディショニングの選択肢です。
- パフォーマンスを高めたい方
- 繰り返す不調や痛みを根本から整えたい方
- メンタルの波やモチベーション低下に悩む方
一人ひとりの状態に合わせた丁寧な認知行動療法と個別プログラムで、心と身体を整え、本来の力を引き出すサポートをいたします。
オーバートレーニング症候群
オーバートレーニング症候群とは
 スポーツ活動などによって生じた生理的な疲労、精神的な疲労が十分に回復しないまま積み重なり、常に疲労を感じる慢性疲労状態になることです。
スポーツ活動などによって生じた生理的な疲労、精神的な疲労が十分に回復しないまま積み重なり、常に疲労を感じる慢性疲労状態になることです。
スポーツでは日常生活で行う活動よりも負荷の高い運動を行い、トレーニングの効果をあげます。しかし、トレーニング後の疲労の回復が不十分であったり、十分な栄養と休養がとれていない場合は、期待される競技成績やトレーニング効果が得られなくなってしまいます。
これは肉体的・精神的なストレスによって、脳の「視床下部」や「脳下垂体」と呼ばれる部位から分泌されるホルモンのバランスが崩れることによるものだと考えられています。
オーバートレーニング症候群の症状は、段階的に進んでいきます。
- 軽症:日常生活上での問題はなく、競技での成績低下がみられるようになります。トレーニングの負荷が大きくなると、身体が思うように動かず疲労を感じるようになります。
- 中等症:だんだんと軽い負荷のトレーニングでも身体が思うように動かなくなってきてつらく感じ、日常生活で疲れやすくなります。
- 重症:ほとんどトレーニングができなくなります。日常生活においても易疲労性、全身倦怠感、睡眠障害、食欲低下、体重減少、集中力の低下、安静時心拍数の増加、血圧の上昇、運動後の血圧が回復する時間の遅延などの症状がみられます。さらには、気持ちの落ち込みや活気がなくなるなど、精神的な症状までみられることもあります。
オーバートレーニング症候群の診断
貧血や感染症などの病気にかかっていないのに、安静時心拍数の増加、安静時血圧の上昇、運動後の血圧の回復の遅れなどがみられ、競技成績の低下、または最大パワーの減少がみられると、オーバートレーニング症候群と診断されます。
- 起床時の心拍数が1分間に10拍以上増加している
- 筋肉痛や疲労がなかなか回復しない
- 風邪などの感染症にかかりやすくなる
- 安静時の血圧が上昇する
- 意欲が低下する
- 食欲低下
- 寝つきが悪くなる
- イライラする
- 抑うつ など
オーバートレーニング症候群の治療
オーバートレーニング症候群の治療は、トレーニングを控えて身体をゆっくりと休め、バランスの良い食事を摂ることです。ビタミンB群やビタミンCを摂るとよいといわれています。症状が重くなると回復にかかる時間も長くなるため、早期発見・早期治療が大切です。起床時の疲労感がなくなるまで休養が必要となります。
治療の原則は、「完全休養」です。月単位で休息をとり、疲労の回復を優先させながら、一つ一つの症状に合わせて治療を進めていきます。必要に応じて、薬物療法も行います。疲労感が改善したら、少しずつ運動を再開していきます。
オーバートレーニングの予防
予防には、適切な目標設定、トレーニングの負荷を競技者の身体の状態と性格特性に合わせて、調整していくことが大切です。
ストレスに気づくことやうまく対処していくスキルが役に立ちます。適切なトレーニング負荷と休養、栄養のバランスをとるなどのセルフマネジメント能力を高めるために、当院のメンタルコーチングを活用ください。
オーバートレーニングはトップの競技選手だけではなく、どの競技レベルにおいても、つまり一般の人にも見られる症状です。疲れが残ったままトレーニングを重ねても効果はありません。健康的な生活を送るためにも、普段から運動と十分な睡眠と栄養を摂るよう心がけましょう。
2週間~1か月程度、運動を控えても改善が見られない場合は、受診を考えるタイミングとなります。抑うつ症状が出て、日常生活に支障をきたすようであれば、受診をお勧めします。
- 体調がすぐれない
- これまでどおり運動ができない
- 体力が回復しない
- 気分がのらない
- 眠れない
アスリートのキャリアアップ・コーチング
アスリートとしての競技人生には、必ず「引退」という節目が訪れます。しかし、その後の人生をどう歩んでいくか、何を目指していくかについて、明確なビジョンを持つことは容易ではありません。
競技という明確な目標を失ったとき、「喪失感」を感じる方も多く、アイデンティティの揺らぎや、社会での役割への不安が生じ、抑うつ状態に陥ることもあります。
当院では、そうした不安や葛藤を丁寧に受け止め、第二の人生を主体的にデザインしていくための支援を行っています。
アスリートの引退とは ― 新たな人生のスタートに向けて
アスリートの引退とは、競技生活に区切りをつけ、次のステージへ進む大きな転機です。これはプロ選手に限らず、高校・大学で活躍した学生アスリートにも当てはまります。
引退の背景には、年齢による体力の低下や怪我、モチベーションの変化、進学や就職といったライフイベントなど、さまざまな理由があります。中には、思うような成績を残せず、経済的な事情から引退を決断するケースもあります。
アスリートが引退を選ぶ主な理由
- 体力の衰え:年齢や疲労の蓄積により、パフォーマンスの維持が難しくなる
- モチベーションの低下:長年の競技生活による燃え尽きや、目標達成による空虚感
- 怪我:大きなケガや、慢性的な痛みにより競技継続が困難になる
- 年齢的な限界:プロでは20代後半〜30代で引退するケースが多い
- 収入の問題:結果が出ず、競技に専念する経済的余裕がない
- 家庭や学業の事情:家族のサポートや進路変更なども影響する
引退後に訪れる心と身体の変化
アスリートとしての生活から離れると、以下のような変化が訪れるかもしれません。
- 身体面:筋肉量の減少や代謝の低下、怪我の後遺症など
- 精神面:アイデンティティの喪失、将来への不安、目標の喪失
- 生活の変化:新たな進路への挑戦、働くことへの適応
引退後の人生をどう描くか
引退は「終わり」ではなく、「新たなスタート」です。これまで培ってきた経験は、指導者やトレーナー、起業家、会社員など、さまざまな分野で大きな力になります。
引退後の生活を前向きに過ごすためには、次の目標を見つけることが重要です。キャリアや人生設計を早い段階から考え、準備しておくことが、充実したセカンドキャリアにつながります。
引退後の不安・悩みに寄り添う
- 自分には競技以外に何ができるのか分からない
- 引退したら周囲からの注目がなくなりそうで怖い
- 一般社会に出るのが不安
- 会社勤めに向いているとは思えない
こうした率直な声に、私たちは誠実に向き合います。
主なサポート内容
自己理解と価値観の再確認
キャリアは「何をしたいか」だけでなく、「自分は何に価値を感じるか」が軸になります。
心理検査や対話を通じて、自分の強み・性格・大切にしたいものを見つめ直します。
スポーツ経験の言語化とスキル転換
アスリートとして培ってきた「忍耐力」「集中力」「自己管理能力」などの資質を、ビジネスや教育、医療など多様な分野に応用する視点を持ちます。
認知行動療法の方略を使いながら、これまでの歩みを「実績」としてとらえ、将来の「強み」として他者に伝えられるように支援します。
メンタルサポート
キャリア支援と並行して、心の安定も大切にします。
「喪失感」「競技への未練」「周囲の期待」といった感情の整理を心理師がサポートします。
一人ひとりに合った“その人らしい”未来を
私たちは「その人がもう一度、自分らしく生きること」をゴールに据えています。
引退は終わりではなく、新しい人生のスタートです。
その一歩を、自信と納得感をもって踏み出せるよう、心とキャリアの両面から伴走します。
まずはお気軽にご相談ください。
アスリート・運動愛好家のメンタルコーチング
公認心理師によるパフォーマンス向上のためのメンタルコーチング
より良いパフォーマンスのための統合プログラムです。
個人、および組織のパフォーマンス向上を目的とした統合プログラムとなります。
個々の特性、現状のアセスメントを4つの領域(身体―精神―認知―行動)から評価した結果に基づいて、個別にケースフォーミュレーション(事例定式化)を行い、適切なサポートを提供します。
コンディショニング
 パフォーマンスを向上させるためには、活動と休息のバランスが重要です。特に、睡眠障害・不眠症はパフォーマンスを下げる最大の要因になります。
パフォーマンスを向上させるためには、活動と休息のバランスが重要です。特に、睡眠障害・不眠症はパフォーマンスを下げる最大の要因になります。
当院は、睡眠障害への医学的対応と共に、心と身体の両面にやさしくアプローチする新しいコンディショニングサービスを提供しています。
**次世代型マッサージ機器「ネオヒーラー」**を使った施術で、心身をリラックスへ導きます。
ネオヒーラーとは?
 ネオヒーラーは、人の手による「さする・押す・軽く叩く」といった手技に加えて、**ごく微弱な電流(マイクロカレント)**を身体に届けることで、血流や神経系に働きかける次世代型のマッサージ器です。
ネオヒーラーは、人の手による「さする・押す・軽く叩く」といった手技に加えて、**ごく微弱な電流(マイクロカレント)**を身体に届けることで、血流や神経系に働きかける次世代型のマッサージ器です。
マイクロカレントとは?
マイクロカレントは、もともと身体の中に流れている生体電流に近いごく微弱な電流のこと。
細胞レベルでの回復力をサポートするとされ、医療やアスリートのリカバリーケアにも応用されています。
マイクロカレントの主な効果
- 血行促進、冷えやむくみの改善
- 筋肉の緊張緩和、慢性疲労の軽減
- 自律神経のバランス調整
- 組織の修復や細胞活性のサポート
クリニックでネオヒーラー施術を受けるメリット
① 自律神経の調整で心の不調にアプローチ
多くの精神的不調(不安・抑うつ・不眠など)は、自律神経の乱れと深く関係しています。
ネオヒーラーは、頭部・背部・手足の末梢に物理的な刺激を与えることで、副交感神経を優位にし、過剰な緊張や交感神経の興奮を抑える効果が期待されます。これにより、薬物療法だけでは届きにくい身体感覚レベルの緊張や不安を和らげるサポートが可能です。
② 「身体から整える」ことによる心身一体のケア
クリニックに来院される方の多くが、肩こり・頭痛・倦怠感・胃腸の不調などの身体症状を同時に訴えられます。
ネオヒーラー施術は、そうした身体のこわばりや不調を軽減します。
③ 信頼できる専門医療環境で受けられる安心感
一般のリラクゼーションサロンと異なり、精神科医や心理師がいる医療機関の中で行われる施術は、心の状態や薬の影響なども加味しながら安心して受けられる点が大きなメリットです。